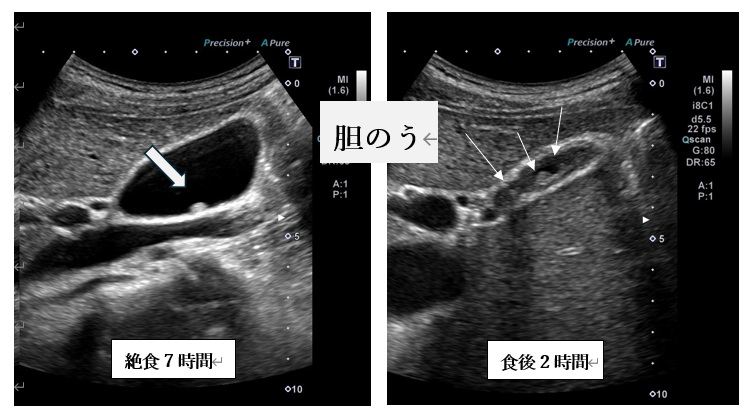「いきいき健康講座」
森下記念病院スタッフブログをご覧の皆様、
こんにちは透析室看護部です。
今回は職員3名(私と、管理栄養士、理学療法士)が、地域の高齢者対象の健康講座に参加し、講師として介護予防に関する講話を行った様子をお伝えしたいと思います。
ところで、最近よく耳にする「フレイル」という言葉をご存知ですか?
簡単に言えば、「介護を必要とするほどではないけれど、完全に元気ではない状態」を言います。
特に注意が必要な世代は、70代後半から80代と言えばイメージできると思います。
医学的に「虚弱」又は「衰退」の意味を含み、適切な取り組みで改善が期待され、放置すれば介護が必要になると言われています。
そのため、予防する取り組みは健康寿命を延ばす上でとても重要なのです。
今回は、健康寿命を延ばすための管理に関心を持って頂くことを目的に行なわれました。
6/23〜7/7 毎週月曜日、連続3回でテーマは「いきいき健康講座」です。
当院から徒歩10分の「東林第1包括支援センター」さんで行われました。
80代が中心の約15名が参加され、全3回欠席者なく熱心に耳を傾けてメモをしたり質問したり、意識の高さが伺えました。
それぞれ各30分ずつ担当し、途中で休憩をはさみながら計90分です。
具体的な内容は、腎臓専門病院の立場から最近話題の「寿命を決定する」と言われる腎臓を守るセルフケアを中心に、
- 「看護師」からは、高血圧の腎臓に与える影響と血圧測定に関する注意点。
- 「管理栄養士」からは、身体の機能を維持するための食べる工夫や、栄養成分表示の見方。
- 「理学療法士」からは、身体を動かす機能を大事にする意味や強くするためのセルフトレーニング。
他にもポイントをおさえた取り組み方法を情報提供させて頂きました。
各回の最後は、全員で椅子に座って出来るエクササイズで終了。皆さんカウントを声に出して筋を伸ばしたり縮めたり。全員で声を出して行う体操は一体感さえ生み出すような雰囲気で、終わった後は心地よい爽快感!




このように、私達は地域とのつながりを大切に、社会参加する活動も少しずつ始めています。今まで以上に地域で暮らす方々の健康を守る病院でありたいと願います。この講座は3ヶ月後(10月)取り組んだ成果を確認し合うフォローアップの回も予定されています。参加された約15名の皆さん、東林第一包括支援センターの御担当者様、暑い夏を乗り切り、3ヶ月後も笑顔でお会いしましょう!