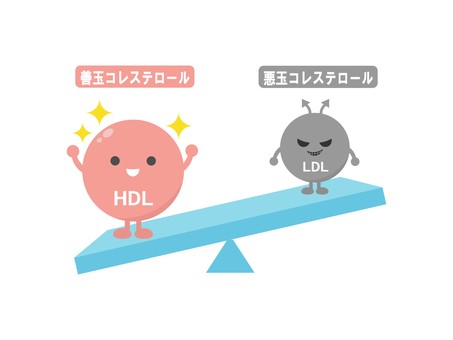<その方らしさ、その人らしさ>
森下記念病院スタッフブログをご覧の皆様
こんにちは、療養病棟です。
6月14日: 認知症予防の日
この日は、アルツハイマー病を発見したドイツの医師アロイス・アルツハイマーの誕生日である6月14日にちなんで制定されました。
9月: 世界アルツハイマー月間
9月21日は「世界アルツハイマーデー」として、認知症への理解を深めるための活動が行われます。日本でも2024年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるために、毎年9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定めています。
DDST:
Dementia・Delirium Support Team(認知症・せん妄サポートチーム)の略称です。
入院中の認知症患者や、せん妄状態の患者のケアをサポートするチームを指します。
当院では4月に認知症サポーター講習会を行いました。多くの方に参加をいただきました。
また、認知症認定看護師の方に介入していただき、症例相談を行いアドバイスしていただき、日頃の看護に役立てています。
療養病棟は、長期にわたり入院される患者様で、生活の場となっています。ご家族の思いも含め、その方らしさに触れ、その人らしくを大切に過ごしていただけたらと思っています。
病棟での日頃の様子を少しご紹介いたします。
ある日、床頭台に置いてありました。ご家族が持参されました。「すみつぼ」というもの。
大工の棟梁であった患者様がご自身で作られたものだそうです。何十年も大切にされていたもの。



ある日、ご面会後奥様がホワイトボードに
「日本ダービーがあります。15時からフジテレビ「みんなのKEIBA」を見せてください。昔から競馬をよく見ていました。」
とメッセージがありました。
時間になったらセット、ずっと観てはいられなくとも、イヤホンで聴いています。寝てしまうことも多いですが。
ある日、CDを聴かせて下さいと。
ご本人と相談しながらセット。美空ひばり、高橋真梨子、坂本冬美、藤圭子など。イントロクイズのように歌手名、曲名を当てたり、一緒に歌ったり。
ある日、日曜日12時NHKつけてくださいと。
「のど自慢」が好きだから。毎週のど自慢を楽しみにテレビカードを準備しておく方もいらっしゃいます。
ある日、お菓子!との希望。
先生の許可を得て、売店に行きお菓子を購入。
クッキーやお煎餅を食べ、お茶を飲む。
美味しそうに召し上がり笑顔。
ある日、食欲がないようだったので、食べたいものを伺うと、「やなぎ」と仰いました。
無知で恐縮ですが、ご本人に伺うと高級魚であると。調べてみると、「やなぎかれい」でした。ご家族に伺うと、福島県のご兄弟から一夜干しのやなぎかれいが送られてきており、幼少の頃から食べていたそうです。時期は冬だそうなので今は入手困難ですがご兄弟にもご協力して頂き、少しでも持参していただくよう準備中。
猫の写真、ご家族との写真、母の日のカード、お誕生日のメッセージなど…ベッドの周囲に多く飾られております。
少しでも穏やかに過ごせるように、今後も「その方らしく、その人らしく」を大切にしていきたいと思います。